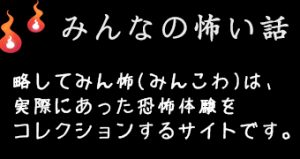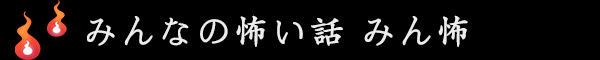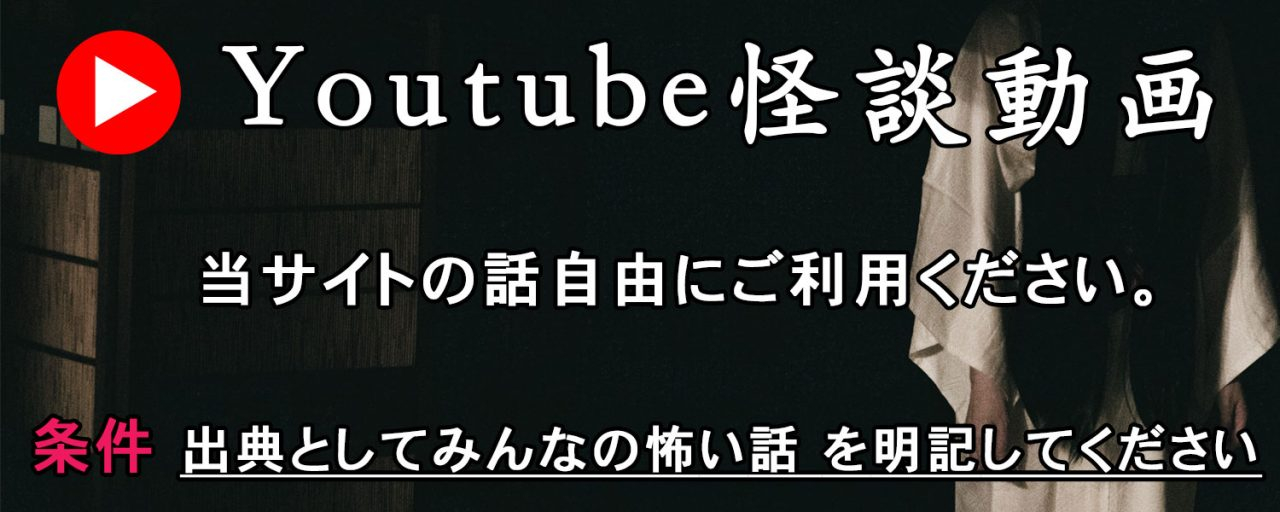52歳 タクシー運転手 男性 にゃんたろうさん 奈良県で本当にあった怖い話
私は奈良県五條市にあるタクシー会社に勤めている、52歳のドライバーです。
この道もかれこれ20年以上になります。
毎日、同じような道を走り、同じような駅前でお客さんを待つ日々ですが、時折、思いがけない出来事に出くわすことがあります。
あれは、去年の秋も深まった頃の話です。
朝晩は冷え込みが強くなり、山の木々も赤や黄色に色づいていました。
今でも忘れられません。
あの夜、私は“乗せてはいけなかった”人を、確かに乗せてしまったのです。
十津川村まで
その日、私は五條駅のロータリーで、夜のラスト客を待っていました。
時刻は22時過ぎ。乗り場も静まり返り、他の車も引き上げていきました。
そろそろ帰ろうか……そう思ったとき、一人の女性が現れました。
ロングの黒髪、白いシャツにベージュのカーディガンを羽織って、手には古びたトートバッグを提げていました。
20代前半くらいでしょうか。少し疲れたような、でも凛とした雰囲気をまとっていたのを覚えています。
「こんばんは」と、少しだけお辞儀をして乗り込むと、彼女はこう言いました。
「十津川村まで、お願いします」
一瞬、耳を疑いました。
五條から十津川村までは、国道168号を南へ1時間半以上。夜の山道は暗く、場所によっては街灯もない。
時間も時間ですし、正直、ちょっとためらいました。
「えっと……十津川のどのあたりまででしょうか?」
彼女は、静かに言いました。
「山の奥の方なんです。昔、ちょっとだけ人が住んでた集落があって……今は、ほとんど誰もいないんですけど」
その一言で、私は察しました。
地元では名前を聞けば「ああ、あそこか」とわかる、かつて人が住んでいた山間の集落のひとつです。
すでに生活インフラもほとんどなく、地図にも載っていない場合があるような場所。
「……かしこまりました」
私は深くうなずき、車を走らせました。
静かな車内と、消えた電波
出発してから、彼女はほとんど喋りませんでした。
スマホも出さず、ただじっと前を見つめて座っている。
途中で一度、「寒くないですか?」と聞いてみましたが、彼女は小さく「大丈夫です」と返しただけでした。
国道168号を南下するにつれ、車の外はどんどん暗くなっていきます。
大塔の山道を抜ける頃には、すでに街灯は数えるほど。
カーナビの地図も、ところどころで反応が遅れ始め、携帯の電波もほとんど入りません。
そんな中でも、彼女は不思議なほど落ち着いていました。
まるでこの道を何度も通ってきたかのような表情でした。
「次の橋、右に入ってください」
十津川村に入ってしばらく経った頃、彼女がふいに声を出しました。
「次の橋、右に渡ってもらえますか?」
言われた通り、国道を外れ、古いコンクリート橋を渡って山道に入りました。
ヘッドライトが照らす先には、うっすらと霧が漂っており、車のタイヤが落ち葉を踏む音だけが響いていました。
「このまま道なりで、10分ほどです」
そう言った彼女の声は、妙に響くような、不思議な抑揚がありました。
山の集落跡地へ
やがて、山の中にぽつんと広場のような場所が現れました。
周囲には誰もいない。建物らしきものも、街灯も見当たりません。
「ここで降ります」
彼女はそう言い、料金をきっちり支払いました。
私は気になって、声をかけました。
「この近くにお家、あるんですか?送っていきましょうか?」
「……大丈夫です。もう、慣れてますから」
そう言って車を降りた彼女は、霧の中へと歩き出しました。
その背中を見送っていると、不意に風が吹き、霧が一瞬だけ晴れました。
――そこには、誰もいませんでした。
確かに彼女はいたはずなのに。
ドアを閉めた音も、歩いていく姿も、全部見ていたのに。
私は急いで車を降りて周囲を見渡しましたが、落ち葉の上には足跡すらありませんでした。
村の記憶
その後、どうしても気になって、地元の郷土史に詳しい知人に相談しました。
彼は少し考えたあと、こんな話をしてくれました。
「十津川の奥にある、昔の集落やろ。今は廃道寸前みたいになってて、誰も近寄らん場所があるらしいな」
「昔、そこに住んでた若い娘さんが、一人で山越えして通学しとったって話もあるわ」
「でもある日、帰ってこなかったんや。あの道、昔からよく霧が出るやろ……」
彼は最後にこう付け加えました。
「その子、きっと今も“帰ってる途中”なんかもしれんな」
それから
それ以来、私はあの山道には近づいていません。
国道168号を走るときも、橋の手前でアクセルを緩めてしまうことがあります。
まるで、また「右に曲がってください」と声が聞こえる気がして。
今でも、深夜の無線にまれに「十津川方面、乗車依頼あり」と入ることがありますが、
確認しても、依頼者の情報が残っていないことが何度かありました。
あの夜、私の車に乗っていたのは、いったい誰だったのでしょうか。
思い出すたび、胸の奥がひんやりと冷たくなるのです。