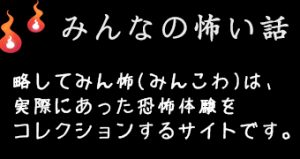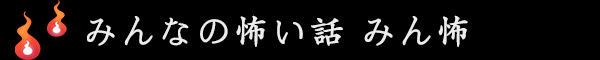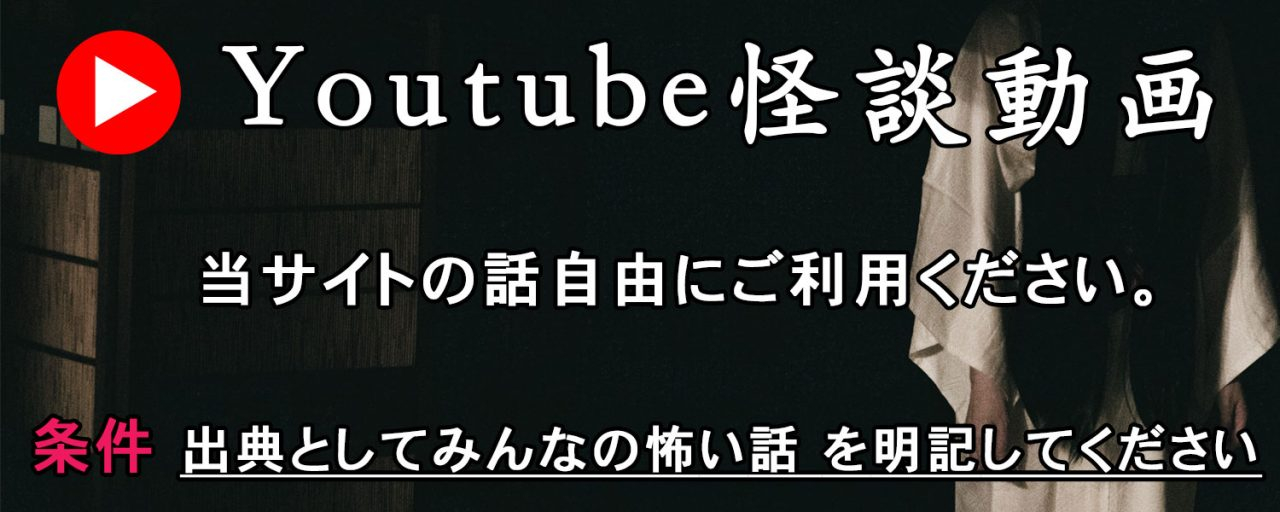私は宮城県の沿岸部にある、人口数千人ほどの小さな町に、去年の秋から暮らしています。震災から十年以上経ってはいますが、復興支援の仕事はまだ続いていて、私はその一環で派遣された形でした。
担当するのは、かつて仮設住宅が建っていた場所に新設された集合住宅の管理でした。風の強い日には海の匂いがして、夜になると人通りがなくなる静かな場所です。
入居者の数は多くありませんでした。私の隣に住んでいたのは、早川さんという30前後の男性で、話しやすく、特に違和感のある人ではありませんでした。東京のIT系の仕事を辞めて、なんとなく移住してきたと言っていた記憶があります。
ただ、一つだけ、最初に地元の人から言われた言葉が、ずっと胸に引っかかっていました。
「海の方を、夜にあまり見ない方がいいですよ。あの辺、ずっと帰ってこれない人たちがいるから」
迷信だろうと笑って聞き流しましたが、今思えば、あのときから何かに巻き込まれていたのかもしれません。
最初の違和感は、生活に慣れてきた頃に始まりました。
帰宅すると、玄関の土間が濡れていたんです。最初は私の靴底かと思ったんですが、雨は降っておらず、床には小さな水の足跡が数歩分だけついていました。裸足のようにも見えました。
一度きりなら気にも留めなかったでしょう。でも、それが何度か続くようになり、ある夜には、濡れた足跡が廊下の途中まで伸びていることに気づきました。拭いても、次の夜にはまた現れる。鍵は閉まっていて、窓も開いていない。誰かが入ってきた気配もない。
それと同じころから、深夜に耳鳴りのような音がするようになりました。
水の音です。びちゃ……びちゃ……と、濡れた足で歩くような、低く湿った音。それが、決まって夜中の2時前後にだけ聞こえるのです。
最初は幻聴かと思いました。でも、その音が壁越しに聞こえてきた日、私は確信しました。隣の部屋からだと。
しばらくして、早川さんの様子もおかしくなっていきました。
目の下にクマを作り、無言でいる時間が増え、ぼーっと窓の外を眺めることが多くなっていきました。心配して声をかけると、ゆっくりとした口調で「……眠れないんですよ。夜中になると、誰かに呼ばれる感じがするんです」と言いました。
「それって夢とかじゃなくて?」
「わからないです。でも、毎晩決まった時間に目が覚めるんです。濡れてる気がして……足が。あと、部屋の中の匂いも……海みたいな、泥みたいな匂いがして」
彼の言葉は冗談ではありませんでした。話しているとき、明らかに体調が悪く、顔色は土気色で、汗をかいているのに寒気がすると言っていました。
一度だけ、ぽつりとこんなことも漏らしました。
「なんで俺、ここにいるんでしょうね……最初はこんなつもりじゃなかったはずなんですけど。なんか、最近、考えがまとまらないっていうか……」
私は心のどこかで、“これは精神的な疲れだ”と片づけたかったのだと思います。でも、早川さんの様子はそれだけでは説明できない変化を見せていました。
ある夜、物音で目が覚めました。時刻は2時過ぎ。壁の向こうから、ぶつぶつと独り言のような声が聞こえます。
「……あけて……さむい……」
思わず玄関から廊下に出て、早川さんの部屋の前まで行きました。チャイムを押すと、数秒後にドアが開きました。
彼が立っていました。
シャツは濡れていて、髪からも水が滴っていました。床にも小さな水たまりができていて、足元は裸足でした。声をかけようとした瞬間、彼はうつむいたまま、私の方へふらりと一歩踏み出しました。
「……寒い……風呂、貸してください……」
その声は、彼の声ではありませんでした。もっと若く、かすれていて、震えている。表情は読み取れませんでしたが、私は、彼の中に“別の誰か”がいると感じてしまいました。
そのとき、不意に私の視界の端に、玄関の鏡が映りました。そこに映っていたのは、早川さんの姿ではありませんでした。
高校生くらいの、痩せた少年のような輪郭。服装も違っていて、濡れた制服のようなものを着ていました。
私は、背筋が凍るのを感じました。彼は続けてこう言いました。
「……あったかいとこ、行きたいんです……もう、寒いのはいやなんです……」
それ以上は聞いていられませんでした。私は震える手でポケットに入っていた小さなお守りを取り出しました。以前、地元の神社で“念のため”に受け取っていたものです。
早川さんは、急に動きを止め、額を押さえてうずくまりました。しばらく呻いたあと、玄関の床にへたり込み、何も言わずにうなだれていました。
私は声も出せず、ただその場を離れ、自分の部屋に戻りました。
震災の幽霊翌朝、彼は何事もなかったかのように出勤していきました。夜のことは何も覚えていないと言い、少しだけ晴れやかな表情をしていたのが、逆に気味が悪かったのを覚えています。
その日以降、彼の異変は収まったように見えました。夜の水音もしなくなり、足跡も消えました。
けれど今でも、夜中に目を覚ますことがあります。窓の外、遠くの海の方を見てしまいそうになるたび、あの言葉が思い出されます。
“海の方を、夜に見ない方がいい”
帰れなかった人たちは、今も誰かの体を借りて、帰る場所を探しているのかもしれません。
そして――その“誰か”に、次は私がなってもおかしくないのだと、時々、思ってしまうのです。