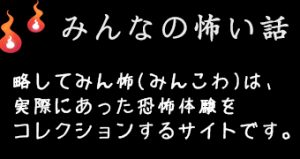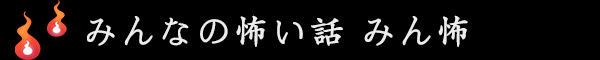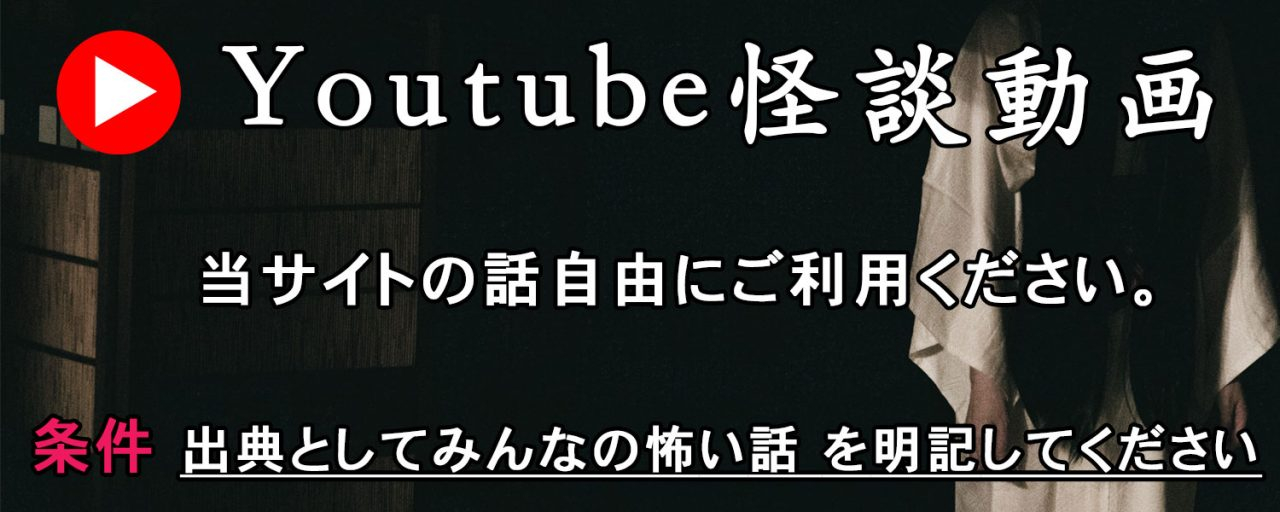大阪市北部、梅田から少し離れた住宅街の一角に、そのコンビニはあった。緑色の看板が目印の、誰もが知る全国チェーンの店舗だ。深夜でも明るく、まるでオアシスのように浮かび上がるその灯りに、ひとり、またひとりと人が吸い寄せられていく。
俺――石田翔太は、そこに勤める大学生のアルバイトだ。時間帯は深夜0時から朝の5時まで。いわゆる“ワンオペ”勤務というやつだ。オーナー夫婦は昼間のシフトに入っており、俺が彼らと顔を合わせるのは月に数回程度だった。
このコンビニに曰く付きの噂なんて一切なかった。事故物件でもなければ、従業員が何かに取り憑かれたなんて話もない。むしろ、開店からずっと平穏そのもの。だが、あの夜を境に、すべては変わった。
最初の異変に気づいたのは、ある冬の深夜2時過ぎだった。
レジの奥で棚卸しの帳簿を眺めていると、店内にふいに「いらっしゃいませ♪」というあの明るいチャイムが鳴り響いた。自動ドアの開閉と連動して流れる、コンビニ特有のあの音だ。
驚いて顔を上げたが、入口のドアは閉じたままだった。防犯カメラのモニターにも、誰も映っていない。
「おかしいな……」
ドアセンサーの誤作動かもしれないと思い、特に気にせずに業務に戻った。が、翌日も、同じ時間に同じように「いらっしゃいませ♪」が鳴った。やはり誰もいない。
連続で起きるとさすがに不気味だったが、システムエラーだろうと自分に言い聞かせた。オーナーに相談してみたが、「夜は冷えるからなぁ。センサーもバグることあるわ」と笑って終わりだった。機械のことは専門外らしく、特に対応するつもりもなさそうだった。
だが、三日目の夜、事態はより奇妙な方向へ進んだ。
例のチャイムが鳴った後、パン棚に近づくと、明らかに潰されたような菓子パンが3つ、並んでいるのを見つけた。袋越しでもわかるほど、上から小さな手でぐっと押しつけたような痕がついている。
思わず「誰かいたのか……?」とつぶやき、背筋がぞっとした。
もちろん、誰かが侵入した形跡はなかったし、防犯カメラにも異常はなかった。だが、俺のスマホでモニターを撮影していた動画には――うっすらと、パン棚の前に立つ“子どものような何か”の影が映っていた。
ぼやけたシルエット、長めの髪、そして膝丈くらいの身長。確かに、そこに何かがいた。
その夜から、毎日3時になると「いらっしゃいませ♪」が鳴るようになった。そしてその度に、棚のパンが潰されていた。だんだんと、それはルーティンのように感じられ始めていた。
ある日、たまたま同じ店舗で夕勤をしている女子大学生の西本にその話をした。「あー、なんかたまに鳴るよね、勝手にチャイム」と、彼女は特に気にも留めない様子だったが、少しして思い出したように言った。
「そういや、あの通り……昔、なんか祠があったって、うちのじいちゃん言ってたわ」
彼女の話によれば、コンビニの場所はもともと地蔵を祀った小さな祠があった場所らしい。再開発で取り壊され、コンビニが建ったのは10年ほど前のことだという。
「その頃から、あそこらへんで車の事故が増えたって聞いたけど、まぁ偶然やろな」
偶然。そう、自分もそう思いたかった。
だが、その夜からはっきりと「声」が聞こえるようになった。
「……あそびたい……」
「……ここ、ぼくの……」
子どもの声。囁くように、パン棚の前で響いていた。
背筋が凍り、俺はレジの奥に逃げた。しばらくして戻ると、今度はレジの上に潰れたパンが置かれていた。まるで「お会計して」とでも言うように。
それでも、オーナーはまったく信じようとしなかった。録音も映像も見せたが、「お前、疲れてんちゃうか?」の一言で終わった。センサーの故障、誰かのイタズラ、それ以上のことは考えたくないようだった。
「霊ぃとか言い出したらキリないで、そんなんより品出しやっといてな」
あの日のあの言葉は、今も耳に焼きついている。
やがて、チャイムは“鳴る”のではなく、“止まらない”ものになった。
深夜3時。いつものように「いらっしゃいませ♪」が鳴ったが、今回は終わらなかった。機械が壊れたように、延々と、繰り返されるメロディ。
「いらっしゃいませ♪ いらっしゃいませ♪ いらっしゃいませ♪」
店内の照明がチカチカと明滅し始め、パン棚から商品が一つ、また一つと落ちていく。冷蔵庫の扉が勝手に開き、雑誌コーナーの本が宙を舞った。
俺はバックヤードに逃げ込み、目を閉じて震えていた。数分後、ふと静かになった気配がして外に出ると、そこには誰もいなかった。
それでも、レジの上にはあの潰されたパンが、きちんと3つ並んでいた。
翌朝、俺はバイトを辞めるとオーナーに伝えた。理由を聞かれたが、「体調が悪い」とだけ伝えた。オーナーは「まぁ夜は合わん人もおるからな」と苦笑していた。
それからしばらくして、あのコンビニの前を通る機会があった。何気なくパン棚を覗き込むと、潰されたパンが、やはり3つ、並んでいた。
今も毎晩、誰もいないその店の中で、「いらっしゃいませ♪」が鳴り続けているのかもしれない。
そしてその音に誘われて、“見えない客”が、今日も来ているのだろう。
オーナーは相変わらず、「機械のバグやろ」と笑っている。
だけど、俺はもう、あのコンビニには二度と近づかないつもりだ。なぜなら、あれはもう、人間が入ってはいけない時間に、別の世界から来る客のために開いている場所になってしまっているのだから――