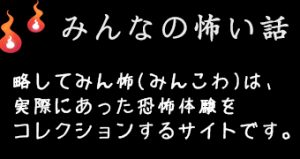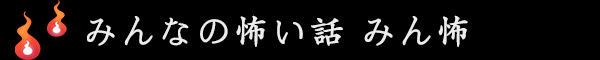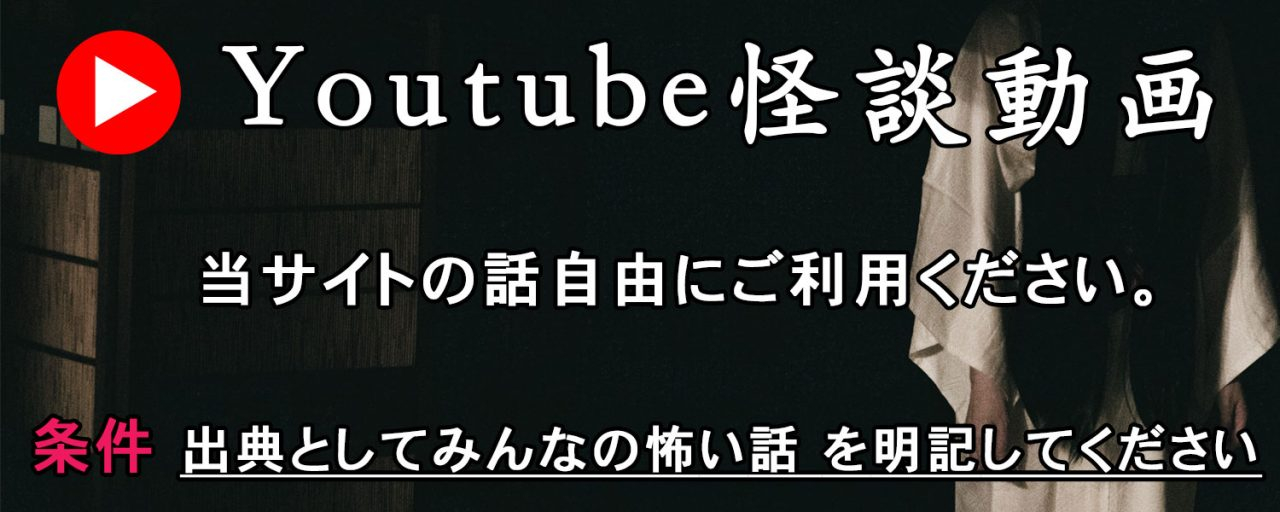あれが本当に現実だったのか、俺はいまでも確信が持てずにいる。
いや、たしかに見た。見たんだ。でも、時間が経てば経つほど、それが夢だったかのように思えてくる。それでも、あの時、俺の心臓が凍りついた感覚だけは、今でも鮮明に覚えている。
すべての始まりは、大学三年の冬、あの日の終電だった。
終電ホームの静寂
その日、俺はサークル活動で遅くなり、先輩とふたりで地下鉄千代田線の西日暮里駅に降り立った。
夜11時45分、終電間際。
俺たち以外にホームに人影はなく、照明は薄暗く、まるで世界が一度停止したかのような静けさだった。
「静かっすね、今日は」
「終電って、こんなもんだよ」
ホームの端に目をやった瞬間、何かがおかしいことに気づいた。
スーツを着た男が立っていた。遠目に見て、最初は普通の通勤客かと思った。
だが、違った。
首が……ない。
いや、頭部そのものがぽっかりと空白になっていた。
俺は言葉を失い、足がすくんだ。
隣にいた先輩がぽつりと漏らす。
「おい……見えてるよな? なあ、お前にも見えてるよな?」
俺はうなずくしかなかった。
男は動き出した。
ガクッ……ガクッ……
体を左右に揺らしながら、不自然な歩き方でこちらに向かってくる。
その歩調が、なぜか痛みに耐えながら歩く人間の姿に重なって見えた。
時間の歪み
俺たちは悲鳴をあげて階段を駆け上がった。改札を抜けて地上に出たときには、全身汗まみれだった。
その日は一晩中眠れなかった。
……だが、奇妙なのはその翌日だった。
朝、スマホを見ると深夜3時半に俺が先輩に送ったLINEがあった。
《なあ、昨日のこと、覚えてるか?》
だが、送信時間を見て俺は息をのんだ。
その時間、俺たちはまだ駅にいたはずだった。
俺はLINEの履歴を遡ったが、そのメッセージの直前に俺が自撮りした覚えのない写真が添付されていた。
西日暮里のホーム。遠くに、あの男の姿がぼんやりと写っている。
撮った覚えはない。構図も奇妙だった。まるで……俺の背後から撮られたような角度だった。
しかも、写真の撮影日時は、2年前の同じ日付になっていた。
どういうことだ……?
俺はスマホを置き、ただ座り込むしかなかった。
繰り返される出会い
二週間ほどして、俺は大学の後輩から一本のDMを受け取った。
「先輩、これ……先輩が言ってた“首のない男”って、こいつのことですか?」
添付されていたのは、Twitterのスクリーンショット。
西日暮里駅のホーム。誰もいない構内に、スーツを着た首のない男が佇んでいる。
投稿にはこう書かれていた。
「深夜、西日暮里駅で。ホームの奥から、不自然な動きの“何か”が近づいてきた。あれ、人じゃなかった。」
背筋が凍った。
写真に写っているのは、あの時の光景と同じ構図。照明の具合、影の落ち方……すべてが一致していた。
まるで、時間が再び巻き戻されたかのような既視感だった。
だが、さらに恐ろしい事実を知ることになる。
その後、ネットで調べたところ、平成13年と平成23年の同じ日付に、24歳の男性が西日暮里駅周辺で刺殺されていたという未解決事件の記事を見つけた。
首元を複数箇所刺された被害者。背中を刺されて命を落としたもう一人の若者。
どちらも未だ犯人不明――しかも、事件が発生した日が、俺があの男を見た日と一致していた。
時をさまよう霊
「もしかして……」
俺は思った。
あの男は、俺たちの“時間のなか”にしか現れない存在なのではないか?
10年ごとに命を奪われた2人の若者。写真の撮影日時と一致するようなタイムスタンプ。2年前のLINE。見覚えのない写真。
――何かが、繰り返されている。
いや、“繰り返させられている”。
あの首のない男は、もしかしたら――
犯人に訴えかけているのではないか?
「ここにいるぞ」
「まだ終わってないぞ」
終わらない夜
それから俺は、夜の西日暮里駅に近づけなくなった。
だが、ある日、ふとした興味で千代田線に乗った帰り道。深夜0時近く、列車は西日暮里駅に到着した。
ドアが開いた。降りようとした俺は、思わず立ち止まった。
ホームの向こう側、壁に張られた広告の隙間から――誰かがこちらを覗いていた。
首のない、スーツ姿の“それ”が。
カツ、カツ、カツ……
足音だけがホームに響いていた。
俺は列車のドアが閉まるのを祈りながら、ただ動けずに立ち尽くしていた。
そして、ドアが閉まる瞬間、そいつが俺の目の前まで来た。
――気づいたとき、俺は自分の部屋で朝を迎えていた。
服のまま、泥のように眠っていたらしい。
だが、スマホには通知がひとつだけ残っていた。
《今夜も行けないけど、応援してる》
見覚えのないアカウント。送信時間は、俺が初めて“それ”を見た時間と一致していた。
それが夢か現実か、誰も答えられない。
だが、ひとつ言えるのは――
あの男は、時間という檻の中で、ずっと彷徨っている。
そして今日もまた、終電間際のホームで、
首のないその姿が、あなたの背後に立っているかもしれない。