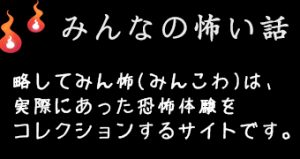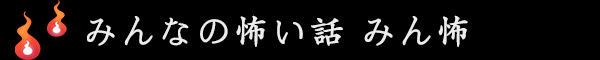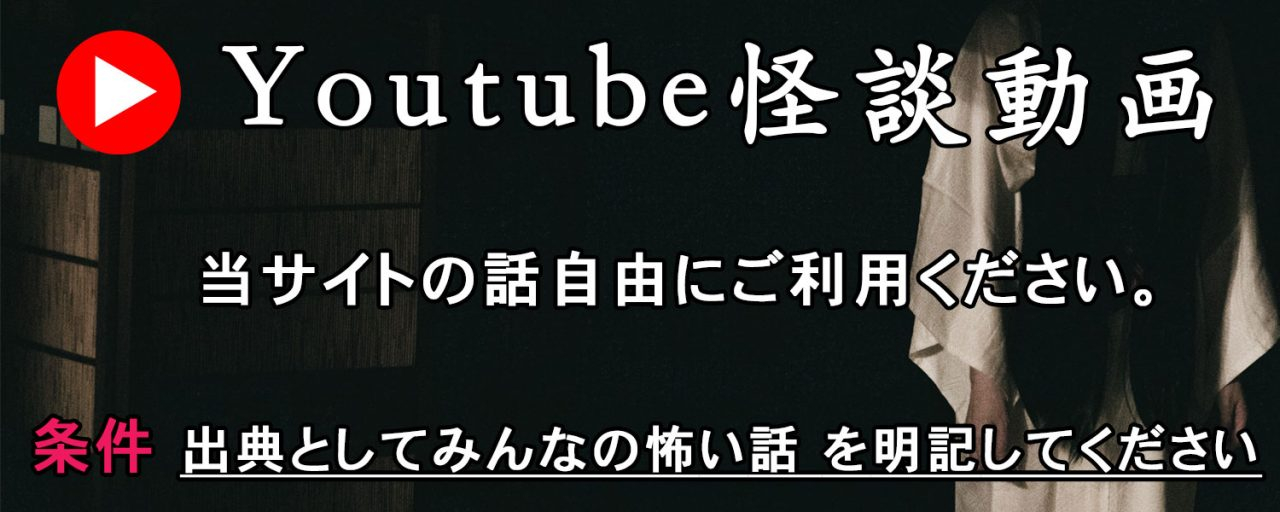私がそのバーに通うようになったのは、ちょうど仕事が立て込んで精神的に参っていた時期でした。
中目黒駅から少し歩いた場所にあるその店は、住宅街の一角にひっそりと佇んでおり、看板も出ていないため、一見するとただの古い一軒家のように見えます。入り口には小さな提灯が吊るされていて、それが唯一「ここが営業している場所なのだ」と教えてくれるものでした。
中へ入ると、照明は抑えめで、壁際には年代物のレコードが並んでおり、スピーカーからは穏やかなジャズが流れていました。客層は落ち着いた年齢の方が多く、会話もささやくような声ばかりで、私はすぐにこの静かな雰囲気に惹かれました。
店主は無口な中年の男性で、話しかけても必要な返事しかしないタイプです。しかし、彼の作るカクテルは本当に丁寧で、口に含むたびにその日の疲れが溶けていくような気がしていました。
通い始めて三度目の夜のことでした。私はいつものように一人でカウンター席に向かいました。ところが、その日は常連客でほとんどの席が埋まっていたのです。
「奥の席、空いてますよね?」
私はカウンターの一番奥の空席を指さして、そう尋ねました。すると店主は、眉一つ動かさず、すっと手を差し伸べて制しました。
「申し訳ない。そこは使っていません」
少し不思議に思いながらも、私は他の席に座ることにしました。その夜は特に変わったこともなく、いつものように一杯飲んで帰宅しました。
ですが、どうしてもその「封じられた席」が気になって仕方がなかったのです。なぜ使っていないのか、どうして誰もそこに触れようとしないのか…。
ある晩、少し酔いが回っていた私は、ついにその席に腰を下ろしてしまいました。
誰に咎められるわけでもなく、私はそこで静かにグラスを傾けました。しばらくして、なぜか背中がひどく重く感じるようになり、薄ら寒さが体を這い回るようになりました。
そのときでした。背後から、コツ…コツ…と、誰かがゆっくりと近づいてくる足音が聞こえてきたのです。振り向きましたが、そこには誰もいませんでした。
「聞こえたんですね」
隣の席に座っていた常連らしき男性が、ぽつりとそう呟きました。
「みんな聞くんですよ。そこに座った人だけが」
私は笑ってごまかしましたが、心の中では恐怖のようなざわめきが収まらなくなっていました。
それからというもの、日常の中に奇妙な影が入り込んでくるようになったのです。
夜、帰宅してシャワーを浴びていると、誰もいないはずの部屋でドアが軋む音が聞こえたり、寝入りばなに金縛りに遭い、耳元で誰かの息遣いを感じたり。
一番恐ろしかったのは、ある晩、自室の鏡の中に自分ではない誰かの姿が映ったことでした。長い髪を濡らした、青白い顔の女でした。私は恐怖で硬直し、その晩は一睡もできませんでした。
翌日、私は意を決して再びバーを訪ねました。店主は私の顔を見るなり、静かに頷きました。
「座ってしまったんですね」
私は無言で頷きました。
「彼女は…この店の常連でした。数年前、あの席にいつも座っていた若い女性です。ある夜、常連の男性客にしつこくつきまとわれていたようで…その後、突然行方不明になりました」
「見つかったんですか?」
「中目黒駅近くの路地で、意識のない状態で倒れていました。病院に運ばれましたが、言葉を発することも、目を合わせることもできなくなっていました。精神的に壊れてしまったのです」
私は思わず言葉を失いました。
「その後、あの席に座った客が次々と体調を崩し、同じような幻聴や幻覚を訴えるようになりました。だから、あの席は“封じた”のです」
店主はそう言うと、私のグラスを下げ、深く頭を下げました。
「すみません。もっと強く止めるべきでした」
私はただその場に座っていることしかできませんでした。
その夜、私は再び金縛りに遭いました。今度ははっきりと見えたのです。目の前に、あの青白い顔の女性が、私の上に覆いかぶさるようにして立っていました。
「…ここにいるの。まだ」
彼女はそう囁きました。
翌朝、私は病院のベッドで目を覚ましました。自宅の部屋で意識を失い、救急搬送されたとのことでした。
「心因性のショック状態でしょう」と医師は言いましたが、私はその理由を説明する気力もありませんでした。
退院後、私はバーへ向かいました。
そこにはもう、あの店は存在していませんでした。建物は取り壊され、更地になっていたのです。隣の住人に聞くと、「あれ?そんな店、あったっけ」と首を傾げるばかり。
私は確かに通っていたはずなのに、その痕跡はどこにも残っていませんでした。
ただ一つ、今でも忘れられないことがあります。
その更地の真ん中あたりに、誰もいないのに風に揺れる椅子の影が、一つだけ揺れていたのです。
今でも私は、中目黒の夜道を歩くたび、その影が再び見えるのではないかと、無意識に目をそらしてしまいます。