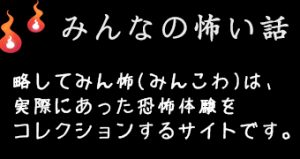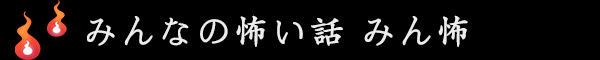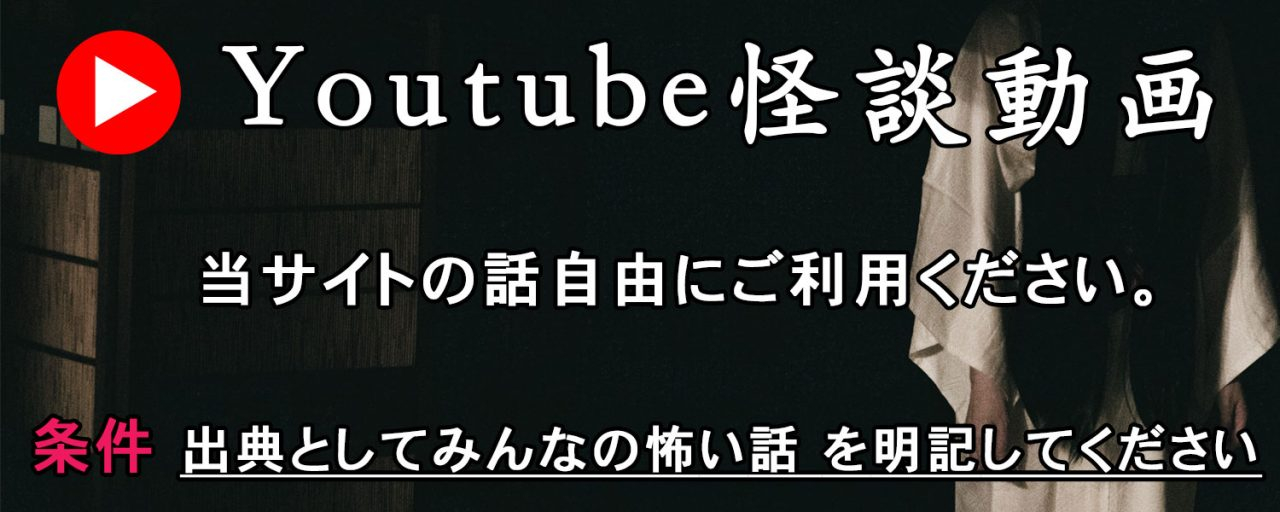「ここ、ずっと空いてるんですか?」
そう私が尋ねたとき、不動産業者の男性は一瞬、目を逸らしました。
「いや、まあ……空いてるというか、空けてるというか……」
その曖昧な返答が、今となってはすべての始まりだったのだと、後から気づきました。
■ 赴任先での仮住まい
私は関西圏の旅行代理店で働いており、3ヶ月間の出張で東京へ赴任することになりました。会社が用意した仮住まいは、品川駅から少し離れたビジネスホテルでした。外観は築30年以上と思われる古びたビルですが、内装はリフォームされており、最低限の快適さは保たれていました。
しかし、チェックインの際、フロントの女性が妙に焦っているように感じたのです。
「……えっと、お部屋は……407号室でございます」
そう言った彼女の声はどこかこわばっていました。カードキーを手渡された瞬間、後ろから別のスタッフがそっと何かを囁いたのを、私は見逃しませんでした。
■ 異様な静けさ
部屋に入ると、意外にも清潔感のある内装に安堵しました。広くはありませんが、ベッドとデスク、小さなテレビ、そしてユニットバス。特に変わった点はないように思えました。
けれど、その夜から違和感は始まりました。
深夜2時頃、突然目が覚めました。理由はわかりません。ただ、部屋の中に「誰かがいる」ような気配がしたのです。時計を見ると2時14分。エアコンの音もテレビの待機音も消え、世界が音を止めたような静けさでした。
次の瞬間、「カツ……カツ……」と、ハイヒールのような音が廊下から響いてきました。
私は耳を澄ませましたが、音は407号室の前で止まり、そして……消えました。
扉の向こうには誰もいませんでした。 peephole(ドアスコープ)を覗いても、廊下は無人。気のせいかと思い直し、再びベッドに戻りました。
■ 調べてはいけないこと
翌朝、フロントで何気なく尋ねました。
「このホテル、ちょっと変な音がするんですけど……」
すると、女性スタッフは一瞬、表情を凍らせました。
「お客様……夜中に、何か見ましたか?」
「いえ、音がしただけです」
「……ご不便をおかけして申し訳ございません。お部屋の変更も可能ですが……」
彼女はそれ以上語らず、私は部屋を変えずに様子を見ることにしました。
ところが、3日目の夜、決定的な出来事が起きました。
■ 真夜中の電話
その夜も、2時を過ぎた頃でした。ベッドの下から「ギシ……ギシ……」と、まるで人が這っているかのような音が聞こえたのです。背筋が凍るとは、あのことだと今でも思います。
勇気を振り絞ってベッドをのぞき込むと、そこには誰もいませんでした。ただ、床に丸く黒ずんだシミが広がっていて、そこだけ妙に湿っていました。
そして突然、部屋の電話が鳴り出しました。
「……はい、もしもし?」
返事はありません。代わりに、受話器の向こうから、女のすすり泣く声が聞こえました。
「……ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい……」
繰り返される声に耐えきれず、受話器を投げ捨てるように置きました。背後から、誰かが私の耳元で囁いた気がしました。
「ここに、まだいるの……」
■ フロントの告白
翌朝、チェックアウトを申し出た私を、フロントの男性が裏に呼びました。
「……407号室に泊まられましたよね?」
「はい。もう無理です。何があったんですか、あの部屋……」
男性は重く口を開きました。
「あの部屋……10年前に事件があったんです。女性の一人客が、チェックイン当日に亡くなられました。自殺とされましたが、状況が不自然で……血痕が残り、床材を何度替えても、黒ずみが浮いてくるんです」
「でもなぜ、使い続けてるんですか?」
「予約がパンパンの時だけ、仕方なく。あと、最近は生活保護の方や長期出張のビジネス客に、訳あり価格で……。407号室だけ、相場より1万円以上安く提供してるんです」
言葉を失いました。私は、その「訳あり価格」の罠に引っかかったのです。
■ そして、今も……
ホテルを出たあとも、あの夜の記憶は鮮明に残り続けています。夜になると、誰かの足音やすすり泣く声が耳元で響いてくるような感覚に襲われるのです。
奇妙なことに、出張が終わって帰宅した私のアパートでも、毎夜2時14分になると、家の電話が鳴るようになりました。
着信番号は「非通知」。出ると、誰もしゃべりません。
ある夜、ふと受話器の向こうで、かすかにこんな声が聞こえました。
「……戻れないの……ここにずっといるの……」
あの女は、407号室で何を待ち続けているのでしょうか。
もしかすると、それを知ってしまった私も、もう――