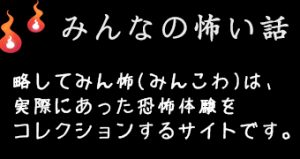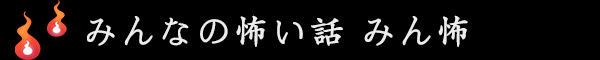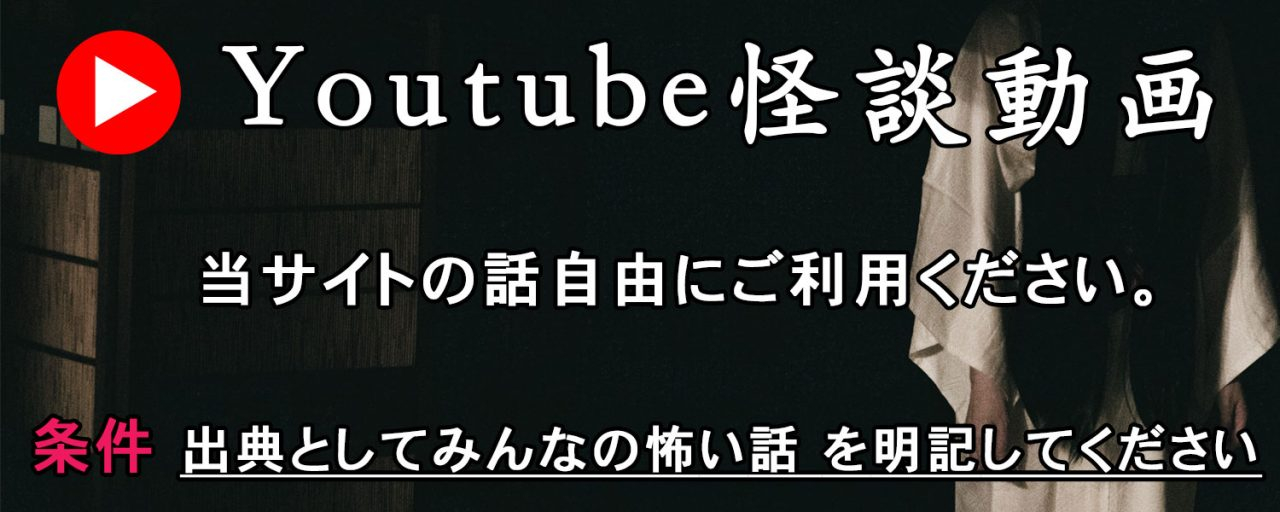その場所は、秩父市の奥――両神山の麓にあった。
山間を抜けるバスがようやく通る道から、さらに獣道のような細い山道へ入る。舗装もされていないその道をしばらく進むと、斜面に沿うように、木々の隙間にひっそりと姿を現す――明治時代に建てられた古い木造の廃屋だ。
鬱蒼と茂る杉と檜に囲まれ、昼間でも薄暗いその屋敷は、まるで時間だけが取り残されたように静まり返っていた。
俺はその時、ある自主制作映画の美術スタッフとして参加していた。普段は映像プロダクションに所属し、CMや短編映画の撮影セットを担当しているが、今回は旧知の監督からの依頼で、ロケ地の選定から現地の設営までを手伝っていた。
タイトルはまだ決まっていなかったが、ジャンルはホラー。廃屋を舞台にしたある一家の崩壊と狂気を描く作品で、「本物の呪われたような場所」を探していた監督が、知人づてにこの廃屋の存在を聞きつけた。
現地を案内してくれたのは、麓の集落に住む管理人の老夫婦だった。
「もう50年以上、人は住んどらんね」
管理人の爺さんは、そう言いながらも鍵束を手に、我々を裏手にある平屋の方へと案内した。そこは母屋とは別棟の、簡素な造りの建物だった。朽ちた木戸を押し開けると、埃と獣臭の混じったような濃密な空気が流れ込んできた。
「この小屋な、昔は“離れ”って言われとってな。……いや、ほんとは“閉じ込め部屋”や」
閉じ込め部屋――俺はその言葉に少し身構えた。
管理人は静かに語り出した。かつてこの地域では、外部との接触が極端に少なく、近親者同士の婚姻が繰り返された結果、精神的・身体的に障害を持った子どもが生まれることもあったという。そして、明治・大正の時代には、そうした子どもを「恥」として自宅に閉じ込める風習――いわゆる私宅監置が、密かに行われていたのだと。
※私宅監置(したくかんち):明治時代から昭和初期にかけて、精神障害者を家族の申請により、自宅の一室などに閉じ込めて監視・拘束する制度。公的施設への入院とは異なり、劣悪な環境での隔離が行われたため、後に廃止された。
「この離れ、窓も鍵も、全部外からしか開けんようになってる。……中に入れるようにするんは、お前さんらが初めてやろうな」
そんな話を聞かされた後では、さすがに気が引けた。だが、監督はむしろ喜んでいた。「最高だ……リアルすぎて逆に怖い」と目を輝かせていた。
撮影は3日間の予定だった。キャスト3名、スタッフ5名という最小構成で、母屋と平屋、それぞれを使ってシーンを分けて撮る段取りだ。
1日目の朝は、搬入と機材チェックに終始した。午後から照明のテストに入ったが、その時、最初の異変が起きた。
LEDライトを母屋の廊下にセットし、監督とカメラマンが位置を確認していた時のことだ。
突然、ライトの前を、何かが横切った。
影……としか言いようのないそれは、人の背丈より低く、獣のような動きで通り過ぎたように見えた。
「誰か通ったか?」
「いや、いま照明テスト中だし、全員ここにいるよ」
念のため外に出て確認したが、誰もいなかった。動物の可能性もあると思い、しばらく警戒していたが、その後のテストでは何も起きなかった。
夜になり、寝泊まり用のテントを敷地内に設置して簡単な食事をとっていると、地元の管理人がふと、夜の山を指差した。
「ほら、あれ見てみぃ」
遠くの尾根に、ふわりと光が灯っていた。焚き火にしては形が不自然で、ゆらゆらと漂うように揺れていた。
「狐の鬼火や。あっこな、昔から人が迷うんや」
それが何なのかはわからなかったが、現場の空気は一気に冷えた。
2日目、母屋の台所で撮影していた最中、また異変が起きた。
録画中、キャストが台詞を言う直前に、台所の隅に置かれたボウルが突然「カラッ」と動いた。振動はなかった。撮り直しを繰り返しても、その瞬間だけ、何かが視界の端を掠めていく。
その夜、俺と照明担当の男が、平屋に機材を置きに行った帰り道のことだ。
「おい……今、中で声しなかったか?」
平屋の中から、かすかに「わらいごえ」のような音が聞こえた。俺たちは顔を見合わせたが、誰も入っていないはずだった。録音機材も動かしていなかった。
中に入って確認すると、誰もいない。だが、部屋の隅――板敷きの床に、小さな手形が三つ、うっすらと残っていた。
誰かがふざけて押した? そうは思えなかった。俺たちは無言のまま、急いでテントへ戻った。
最終日の朝、キャストのひとりが急に具合を悪くし、撮影は一部中止となった。吐き気と動悸を訴えていたが、下山した後には何ともなかったという。
予定を繰り上げて機材を撤収し、全員で母屋の外に並んで最後の確認をしていた時だった。
「いらっしゃいませ――」
どこかで聞き覚えのある、コンビニ店員のような声が、風に乗って耳元で聞こえた。
「今、何か……聞こえなかったか?」
スタッフ全員が顔を見合わせた。
誰も何も言わなかったが、その場にいた全員が、何かが終わりを告げに来たのだと、直感していた。
その後、編集作業中、母屋でのシーンをチェックしていた監督がふとつぶやいた。
「……この影、何?」
モニターの奥、キャストの背後に、誰もいないはずの“影”が立っていた。しかも、それは画面の中でだけ動いていた。
撮影時には見えなかった影が、映像の中で、確かにそこにいた。
いまでも、その映像は残っている。ただ、それを誰かに見せようとは思わない。なぜなら、その影がこちらを見ている瞬間に、一度だけ、俺のフルネームを囁いたような声が入っていたからだ。
あの廃屋は、もう貸し出されていないという。
管理人も亡くなり、道もふさがれ、地図上でも確認できなくなったと聞いた。
だが、両神山の麓、夜にしか見えない鬼火の奥に、今も**“閉じ込められた何か”が、闇の中でこちらを見ている気がしてならない