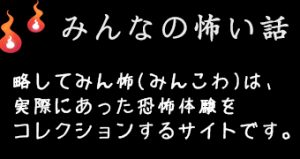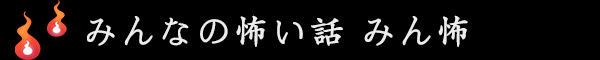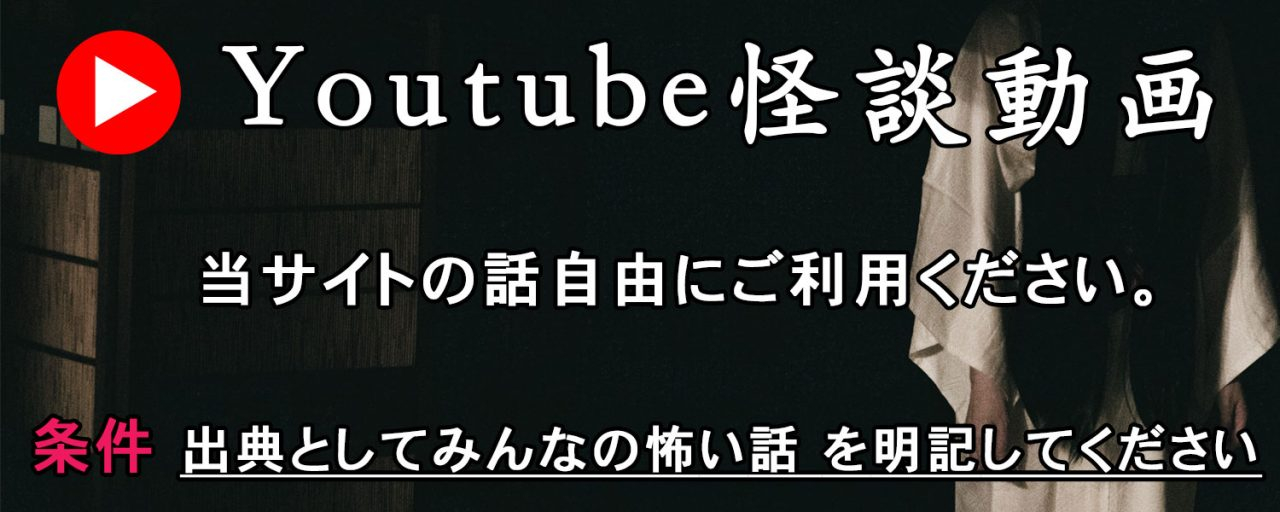僕は、とあるクレジットカード会社のコールセンターで、夜勤のオペレーターをしている。
盗難や紛失の受付窓口は、24時間体制。昼夜を問わず、全国からの通報を受け付けている。
深夜シフトは、いつも5人ほどの体制だ。ヘッドセット越しに聞こえるのは、お客様の焦りや怒り、時には涙声。
毎晩が、少しだけ緊張感のある時間の連続だ。
その日も、特別なことはなかった。
日付が変わって、しばらくするとセンターの中も静けさに包まれていった。周囲では、他のオペレーターたちも無言でパソコンの画面を見つめ、たまに咳払いや椅子の軋む音が聞こえるくらいだった。
僕が「それ」に遭遇したのは、午前3時57分だった。
突然、着信の通知が点滅した。少し遅めの時間にしては珍しくない。
僕はヘッドセットのマイクを口元に寄せて、いつものように応答した。
「お電話ありがとうございます。◯◯カード盗難・紛失窓口です。ただいまお名前とカード番号をご確認させて――」
その時だった。
『かえして』
女の声だった。
それも、ヘッドセット越しではなく、まるで耳の中に直接届くような、不自然に近い声。
「……すみません、恐れ入りますが、お名前を伺ってもよろしいでしょうか?」
何度かそう聞き返しても、返事はなかった。ただ、『かえして』という掠れた声だけが繰り返された。
その瞬間、ふと頭に浮かんだ。以前処理した、事故死されたという女性のカード。
ただ、確認してみると、その方の情報はすでに完全に処理されていたはずだ。社内システム上にも、もうログは残っていない。
数秒後、着信はふっと切れた。
周囲の誰もが沈黙したままだった。たぶん、僕だけが「それ」を聞いたのだろう。
気のせいだと思い込もうとした。
けれど、それが“ただのノイズ”ではないと、すぐに思い知ることになる。
午前4時の少し前、交代で5分ほどの短い休憩をもらい、オフィス横のトイレに向かった。
このビルは築年数が古く、トイレもどこか薄暗くて、タイル張りの壁が冷たさを強調していた。
他のオペレーターは誰もいなかった。僕は個室には入らず、洗面所で手を洗っていた。
水を止めようと手を引いたとき、「コン……コン……」と、奥の個室からノックのような音が聞こえた。
「すみません、使用中ですか?」
反射的にそう声をかけた。でも返事はなかった。
気のせいだったかと首をひねりかけたその時、個室のドアの下から何かが滑り出てきた。
それは、ボロボロになったクレジットカードだった。
濡れていて、裏面の署名欄は滲んでいて読めない。でも、どこかで見た気がした。
思わず手を伸ばそうとしたが、直前で踏みとどまった。
――カードは、絶対に社外に持ち出せないし、トイレになんて絶対にあるはずがない。
ぞくりと背筋が凍った。
そして、洗面台の鏡の中に――僕の後ろに、髪の長い女が立っていた。顔は見えない。
だけど、両手は真っ直ぐ前に突き出されていて、例のカードを握りしめていた。
『……かえして……わたしの……』
それは、あの着信の声と、まったく同じだった。
震える手で目を覆い、どうにかして振り向かずにトイレを飛び出した。
心臓が耳の中で爆音のように鳴っていた。
戻ってから、思い切って先輩のオペレーターに相談してみた。
すると、ぽつりと返ってきた。
「……あー、それ、出たかもな。3か月前、午前4時前に、同じ個室で倒れた人がいたんだよ。
持ってたカードが処理中に紛失して……いまだに未解決らしい」
「じゃあ、あの声は……?」
「さあな。でもな、ここって“電話越しに声を残す”って噂、前からあるんだよ。俺は信じてないけど」
それきり、その先輩は黙ってタバコを吸いに行ってしまった。
結局、僕が見たものが何だったのかは分からない。
ただひとつだけ確かなのは、あの日から、午前4時前の着信だけはどうしても取るのが怖くなったということだ。
今でもたまに、あの時と同じ音声がログに残ることがある。
無音の波形に混じって、小さく、はっきりと。
『かえして』
…次は、誰に届くのだろうか。
この話は、僕が今も働いているあのコールセンターで、確かに体験した出来事だ。
午前3時57分の着信には、くれぐれも気をつけてほしい。